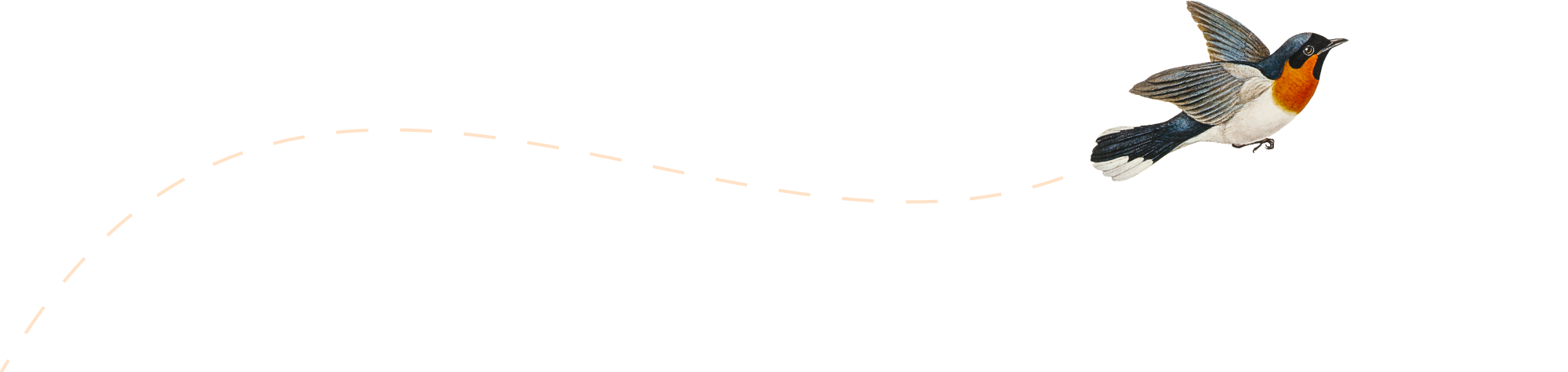楽器をあれこれ試したいとか、買い揃えていきたいという欲求は誰もが通る道かもしれない。ただ、結論を言ってしまうと、何も音楽とは関係していないことなのだ。
テレビやらパソコンのモニターを画面拡張という意味以外で増やしたいと思うだろうか?比べてみたら、少し色も音も違うかもしれない。けれど、同じ部屋にテレビが2台あるという部屋は少なくとも見たことがない。
スピーカーだとなぜか数台ある人はいる。私がそうだ。しかし、当然ながらそのうちの1台ぐらいしか同時に使っていない。
カメラとか時計もコレクションしている人はたくさんいる。これらとスピーカも楽器も同じようなものだ。
カメラも同時に1台しか自分では使えず、時計も1本しかつけている人しか見たことがない。(時計は何本でもつけられるだけつけれるかもだが、そんなことをしている人はそういない)
服も増やしたいと思う人はたくさんいる。同時に着れるのはそれこそ一着だけだ。服の場合は全体とのコーディネートの関係で、あわせるものがそこそこいうという考えはある。
では、カメラや時計はどうだろう。これは完全な好奇心と体験をしたいだけだ。何かしら、違う世界のものを手にいれたらある種の体験ができて、満足が得られるという風に思うわけである。
スピーカーもそうだ。違う体験ができるかもと思ってしまう。
楽器も結局そこにいく。アコースティックの楽器でも同じ音の出るものなんてない。余計にこれはどんな音がするのだろう?と思ってしまう。電子楽器だとメーカーも違えば発音方式も違うし、ユーザーインターフェースも違うので、余計にこれはどんなものなのだろうという好奇心が煽られる。
結局、この好奇心を満たして、新しい体験をしたいがために楽器を増やしてしまうのだ。
しかし、前述したが、これは音楽とはまったく無関係である。
絵をかんがえてほしい。画材を買うが、そこから以降はそれで何をどういう風に描くかだけである。画材の種類、画材メーカによって、何かが違うかもしれないが、普通はその持っている画材でなんとかするだけだろう。
どうコントロールするかの方が大きいのだ。映画だと脚本があって、それを演じる役者がいて、構図があって、時間感覚があって、で、どのカメラで撮っているとかはどうでもいいではないですか。
楽器を増やすことより、いまある楽器をどう使うかを考える方がずっといい。