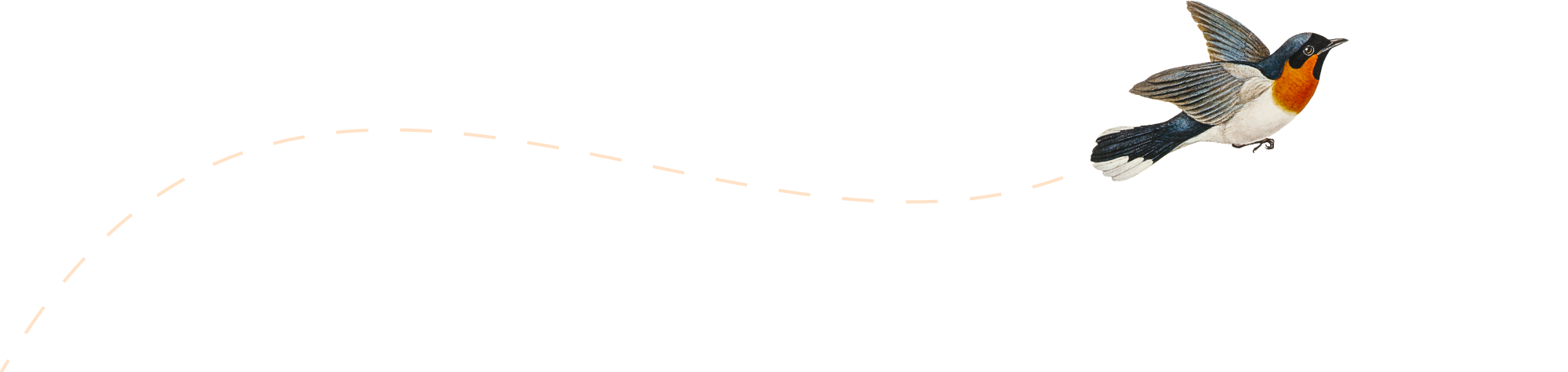デジタルは数字である。数字であるから、計算は常に正解というか答えをだしてしまう。ところが実際にはそうではない。
簡単な例だと1/3は正確には答えがでない。0.33333333…と無限にあるので、数字としては答えがでない。デジタルだと桁数の制限があるので、必ず、答えが出る。
これは単純な計算例だが、デジタルというのは抽象化された世界である。だから、情報は抽象化されている。だから、コピーができる。
実際の情報はどこまでいっても具体がのこっている。デジタルカメラで写真をとったら、その解像度、色深度の情報以外は入っていない。しかし、大方それで役立っている。大昔のパソコンは320×200で高精細と言ってた時代もあった。色も8色しかでなかったこともあった。RGB1ビットだ。現在のようにRGB各8bitになるまで相当時間がかかった。メモリが高かったからだ。また、それらの画像を処理するCPUのパワーも必要だった。今ではあたりまえなんだが。
インベーダーゲームやパックマンが粗い画像なのは、本当に粗かったわけだ。
抽象化された情報でも情報量が多くなれば使える。音楽は44.1KHz、16bitあれば、そこそこ聞ける。
ただし、実際のリアルはそうはできていない。
ソフトシンセを使っているとそういうのはよくわかる。実際のアナログシンセに比べて違うことは何かというと、毎回同じ計算結果なので、同じ音がでているわけだ。
ギターだったらこうはいかない。楽譜どおり正確に弾けたとしても、ピッキングのタイミングや角度によって、あるいは弦の様子で毎回同じ音がでるとは限らない。こうしたことが積み重なってリアルな音がなっているわけなのだ。
大きくは計算結果とはかわらない。たとえば、シシオドシ。竹筒に水がはいっていく、いっぱいになると倒れてカタンという音をだす。このタイミングはおおまかには計算どおりだ。水量もそうかわらんだろう。けれど、おそらく、毎回の音はたぶん微妙に違う。聴き比べてもわからない程度に。もしループサンプリングすれば再現できるかもしれないが。1回のループだとすぐにあきるだろう。本物はあきないと思われる。
この差が大きいのだ。アナログシンセなら何かが微妙になにかに影響しているのだ。それは部品レベルで。大きくは計算どおりでも誤差がそこら中に存在し、電圧の誤差もそこら中に存在し、言ってみれば、毎回及第点の音はでているが、毎回ちょっと違う音が出ているのだ。
この誤差とか相互の影響が何もしないと出ていないのがデジタルの問題その2である。