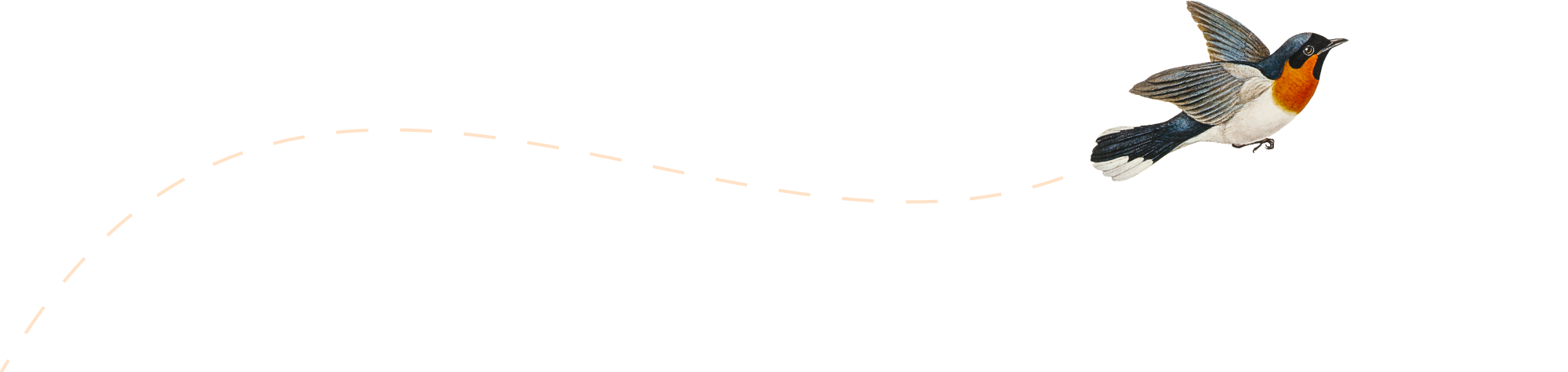ほとんどの人はえらくなりたいと思っていると思う。特に意識高い系といわれる人らはそうだろう。自分のノウハウを人に教えたいというのもそんな感じだ。その気持ちはよくわかる。
大衆はまず間違ったことをしているというのはある。要するに彼らの行動に合理はない。合理がないから、その行動は間違っているとなる。わかる人はそれを教えたい。そう思ってしまう。
しかし、その感じ方も、実はどこまでいっても上には上がいる。で、上になるほど言ってこない。
なんで、もっと偉い人は言わないのか。言っても通じないというのが1つ。もう1つは失敗体験も勉強の内と思っているのが1つ。言わないことで、なにかしら得になることも1つ。言うことで、世界ががらっと変わってしまうのが1つあるだろう。
べらべら話をしていたり、私はわかっていますよ。教えないだけです、といった類も小物である。
けれど、人はえらくなりたいのだ、えらくなって自慢したいのだ。しかし、いろんなことを知れば知るほど、言っても通じないレベルにまず達し、もしこれを人に教えるとなると苦労するなと感じてしまう。
ただ、質問してくる人を邪険にするのもどうかとは思う。ちゃんとその人のレベルで、おもいつくことをアドバイスすべきではある。
けれど、自分から発信しない方がいい。こんなことを書いているようでは駄目だ。